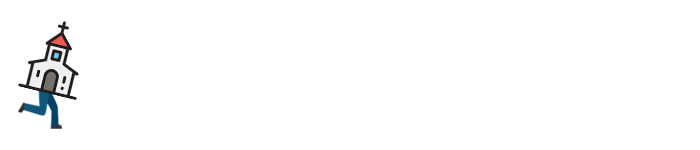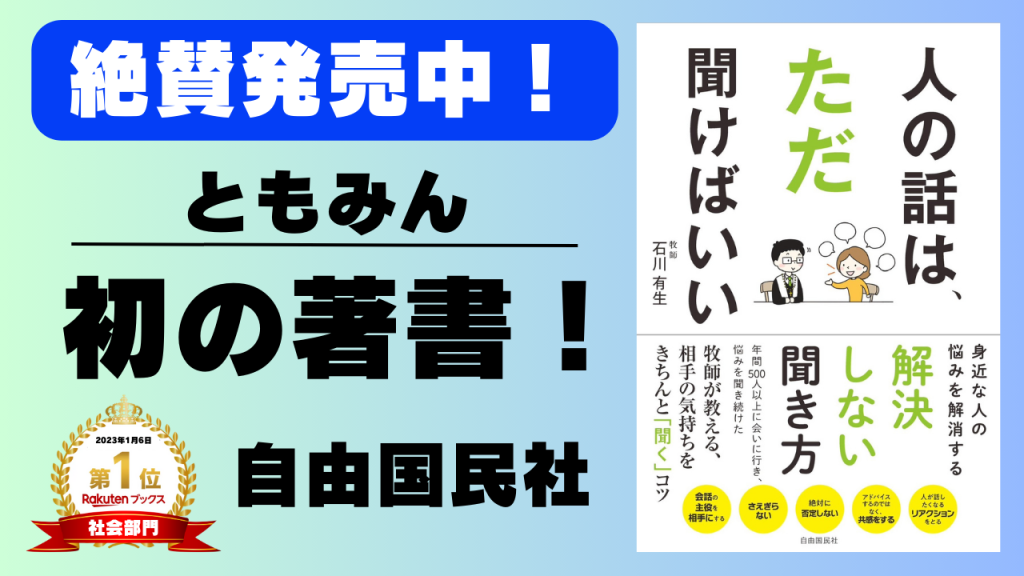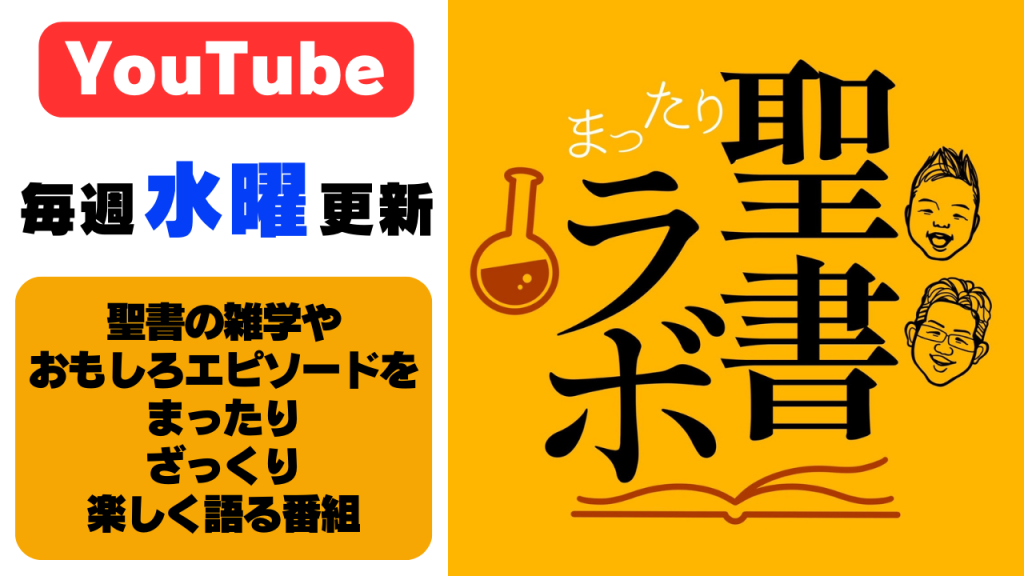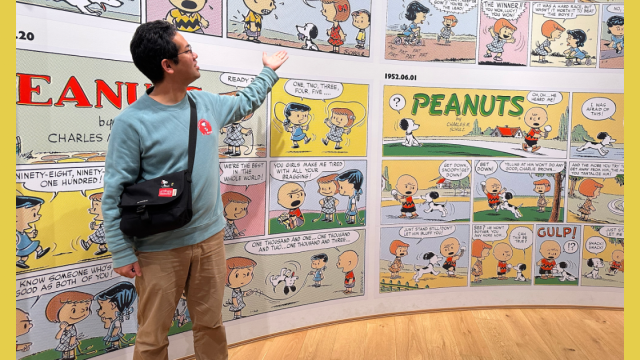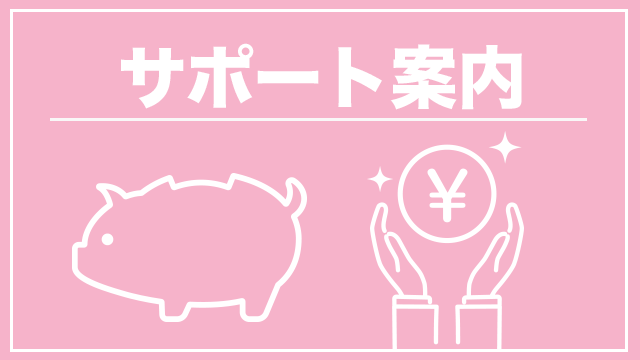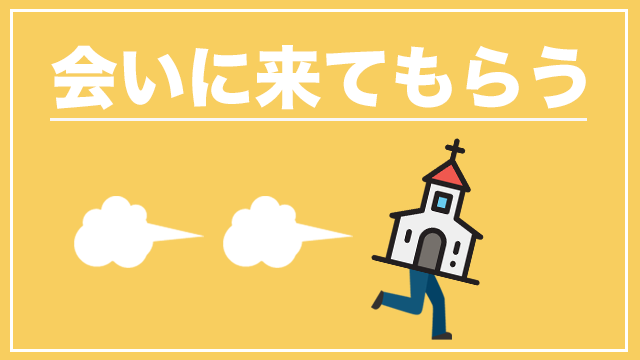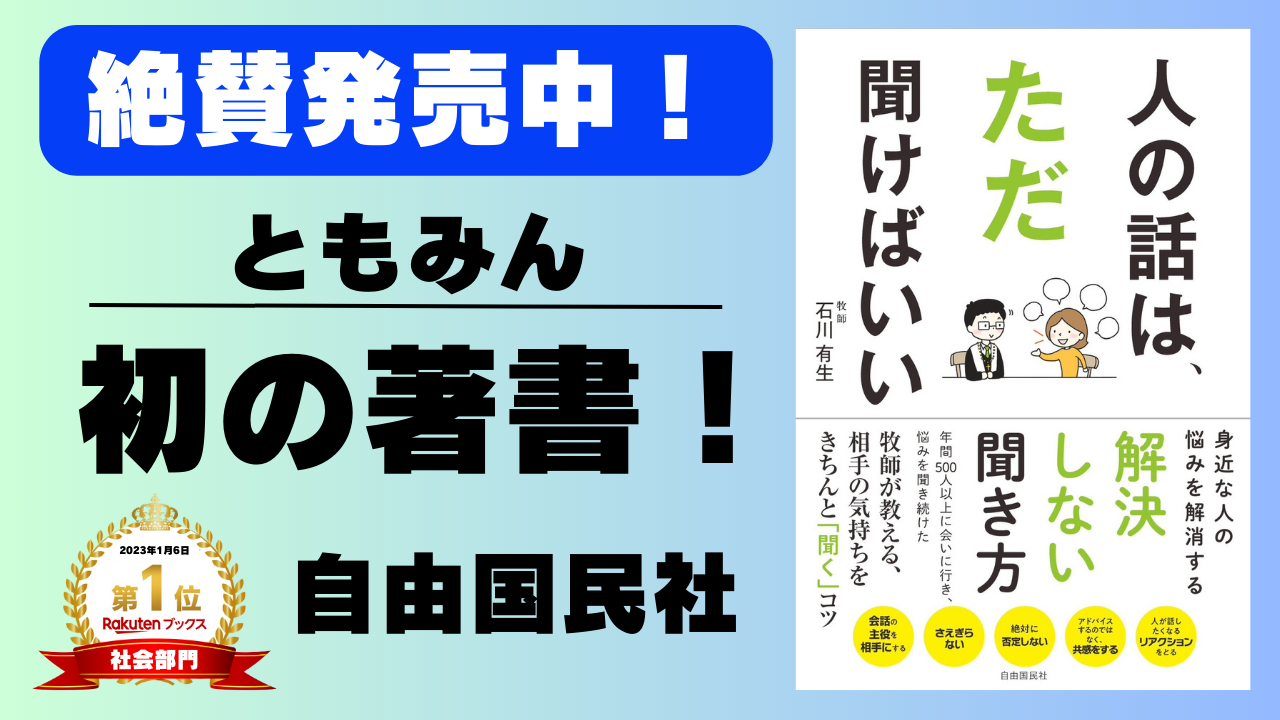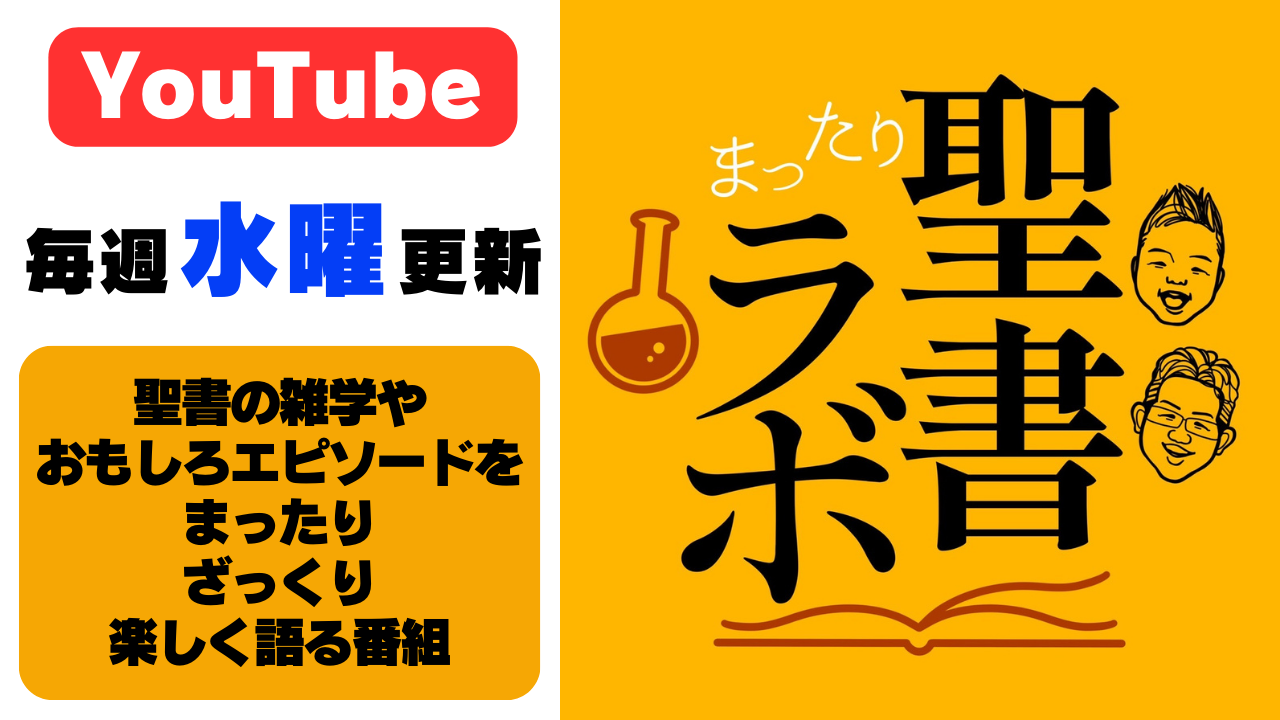健全な教えとは

教会という場所は、神の愛に触れ、癒され、赦されるための共同体であると信じて、多くの人が集います。しかし、「礼拝に来ないのは信仰が弱いからです」「奉仕をしない者に祝福はありません」「教会に従うことが、神に従うことです」といった言葉に心を痛めた人も少なくありません。見える信仰行動だけが重視される空気の中で、来られない人や従わない人が、まるで「信仰がない人」と扱われることがあります。そのような空気に息苦しさを感じ、教会から離れた人、信仰そのものに疑問を抱くようになった人もいることでしょう。
けれど、聖書は本当にそのような信仰のあり方を教えているのでしょうか。「礼拝に来られない人は信仰が弱い」と決めつける言葉は、果たして聖書に根ざした“健全な教え”なのでしょうか。
テトスへの手紙には、「あなたは、健全な教えに適うことを語りなさい」とあります。この“健全”という言葉は、「健康的な」「病んでいない」「命を損なわない」という意味を持っています。つまり、健全な教えとは、人の魂をむしろ回復へと導くものです。聞く人の霊と人格を健康にし、励まし、癒す力を持つ教えなのです。
一方で、「異なる教えを説き、わたしたちの主イエス・キリストの健全な言葉にも、信心に基づく教えにも従わない者がいれば、その者は高慢で、何も分からず…」と、テモテへの手紙一にあります。ここでは、イエスの言葉こそが“健全な言葉”の中心であると明言されています。組織の規則やリーダーの指示、人々の慣習ではなく、イエスご自身の言葉と歩みにこそ基準を置くことが求められているのです。
健全であることは、必ずしも「正論を語ること」ではありません。聖書の言葉を使って人を萎縮させたり、服従させたりするのであれば、それはもう健全ではありません。イエスの言葉は、人を励まし、愛し、赦し、引き上げるものでした。イエスが律法学者やパリサイ人に怒りを示されたのは、彼らが律法の言葉を使って人々を縛りつけ、裁いていたからです。
現代の教会においても、「見える行動」で信仰を測ろうとする傾向があります。「毎週来ないと神に背く」「奉仕をしないのは信仰が弱い」「リーダーに従わない者は神にも従えない」といった言葉がそれにあたります。これらは一見正しく聞こえますが、聖書の文脈から切り離され、人を縛る宗教的コントロールへと変化している危険性があります。
テモテへの手紙二には、「人々は自分に都合の良いことを聞こうと教師たちを寄せ集め…真理から耳を背ける」とあります。この「耳ざわりのよい教え」は、形式に従えば祝福されるといった単純な信仰観や、忠実な奉仕が神の喜びだという一面的な理解にもつながりかねません。本来の福音は、型にはめるのではなく、自由と回復へと導くものです。
聖書は、外側の行動よりも内側の心の変化を大切にしています。ローマの信徒への手紙には、「心を新たにして自分を変えていただき、神の御心をわきまえるように」とあります。たとえ奉仕や出席が途切れても、心が神に向いているならば、神はそれを見てくださいます。逆に、義務感や恐れからの行動は、信仰ではなく、単なる宗教的作業にすぎません。
イザヤ書には「唇でわたしを敬うが、心はわたしから遠い」とあります。これは、形式的な信仰がいかに神の心から遠ざかってしまうかを語っています。イエスが宗教的に熱心な人々を非難したのも、彼らの心が神の愛から離れていたからです。
教会では「御言葉の指導」として語られる言葉が、実は人をコントロールしたり、恐れで縛るために用いられることがあります。たとえば、「他の教会に行ってはならない」「YouTubeの礼拝を見るのは不信仰」といった言葉は、聖書的な根拠というよりも、組織の支配欲から出てくる言葉かもしれません。
エフェソの信徒への手紙には、「悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ、聞く人に恵みが与えられるように語りなさい」とあります。健全な言葉とは、人を責めるのではなく、育み、慰め、自由へと導く言葉なのです。
「あなたももっと奉仕したら祝福されますよ」という言葉も、相手を思う優しさから出た励ましであれば問題ありませんが、そこに「奉仕しない=信仰がない」という評価の視線が潜んでいるならば、それは“呪い”のような言葉に変わってしまいます。箴言には「癒しをもたらす舌は命の木。よこしまな舌は気力を砕く」とあります。私たちの言葉が、命を生かすものとなるように、イエスのまなざしから語られる必要があります。
私たちの信仰は、誰の声に従っているでしょうか。組織の掟でしょうか。それともイエスの御声でしょうか。コロサイの信徒への手紙には、「人間の言い伝えによって人のとりこにされないように」とあります。キリストの御言葉を脇に置いて、人間の言葉を第一にしてしまうとき、それは健全な教えではなくなってしまいます。
イエスは言われました。「わたしの羊はわたしの声を聞き分ける。わたしは彼らを知っており、彼らはわたしに従う」と。イエスは、私たちに直接語られるお方です。組織を通してだけではなく、聖書を通して、祈りを通して、私たちの心に直接語られます。
「教会で傷ついたけれど、神を信じたい」「組織の言葉に混乱したけれど、イエスの声を聞きたい」という思いがあるなら、それはあなたのうちにある聖霊のささやきです。テトスへの手紙には、「教えに適う信頼すべき言葉をしっかり守る人でなければならない」とあります。健全な教えは、従わせるためではなく、傷ついた者を立ち上がらせるための福音です。
健全な教えとは、キリストとの関係が健やかであり、人を支配せず自由にし、育て、癒し、回復させる真理です。真理と愛が共にある場所、それが健全な教えのあるところです。
もし教会や他のクリスチャンが「あなたのため」と言いながら、あなたが自分を責めたり、心を消耗していくようであれば、それは健全な教えではないかもしれません。健全さは、いつもイエス様の愛のまなざしに立ち返ることから始まります。