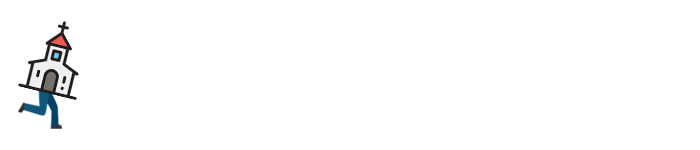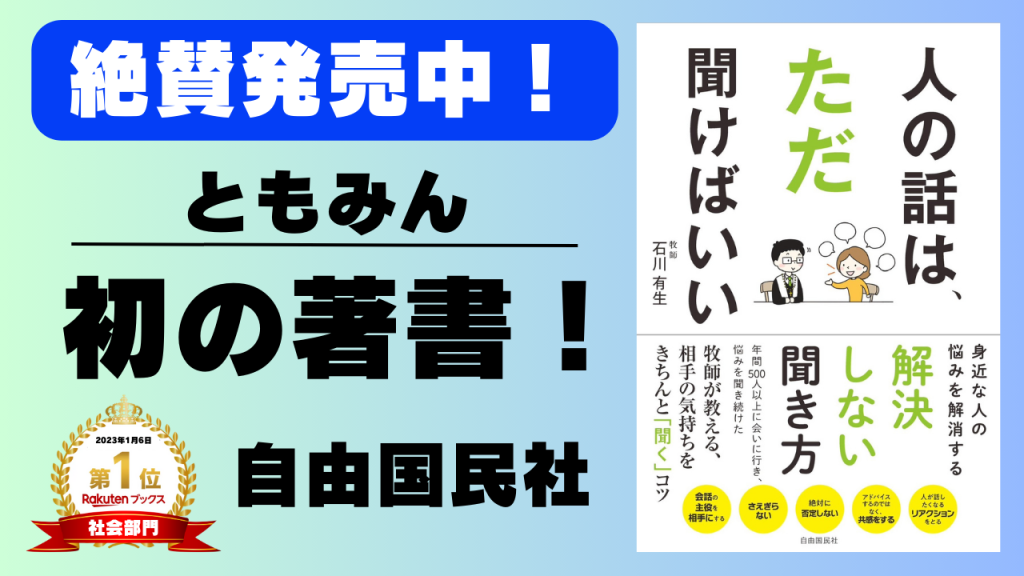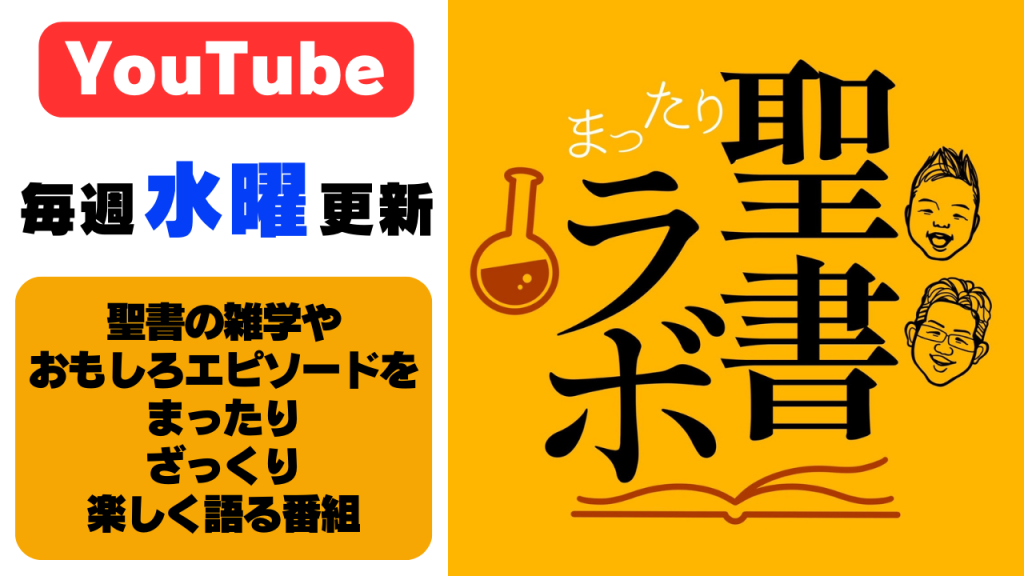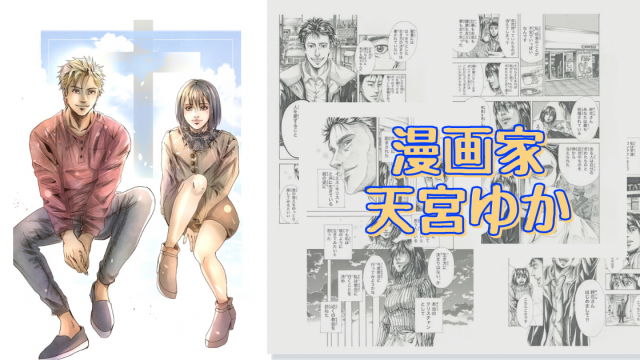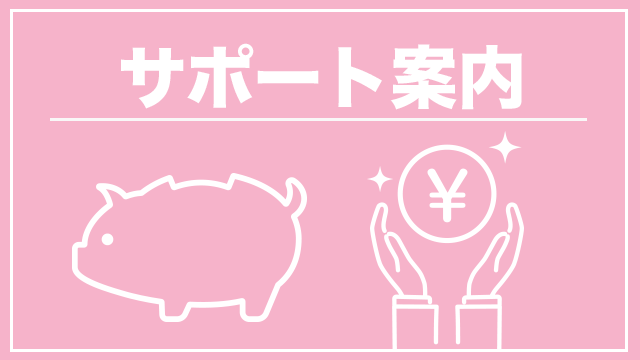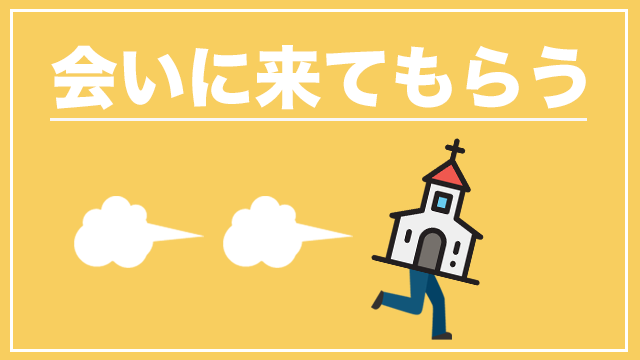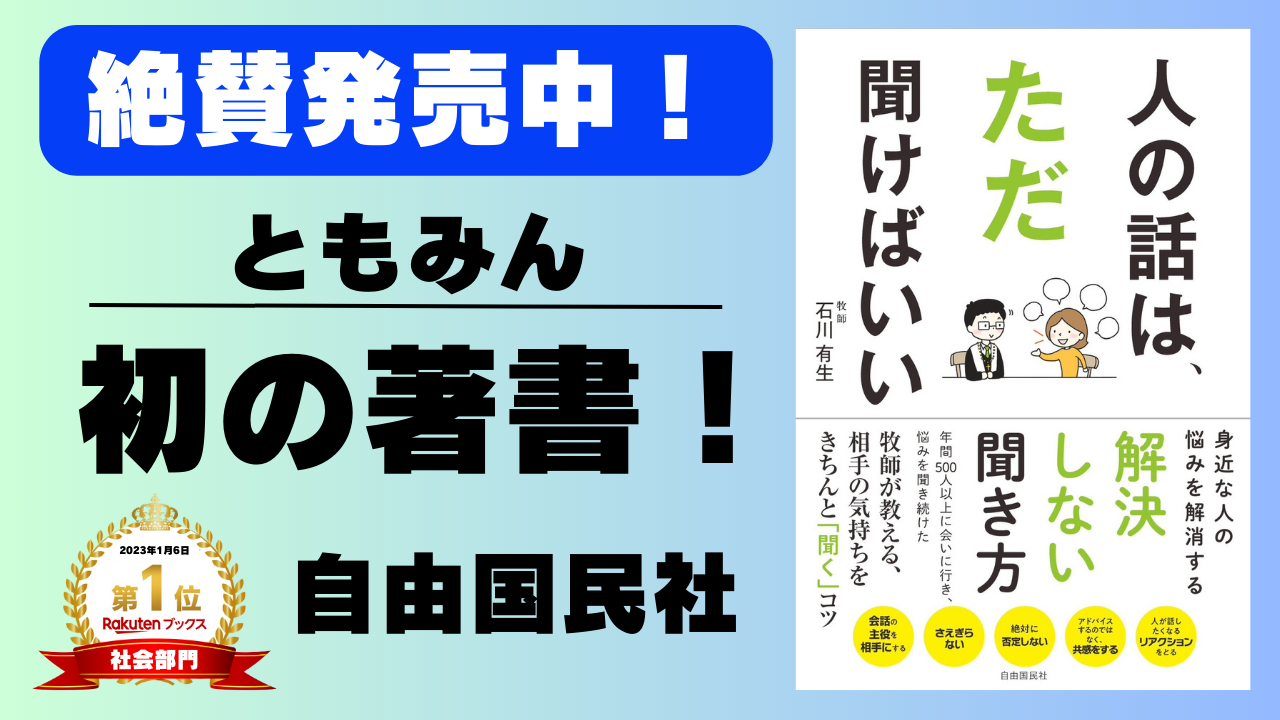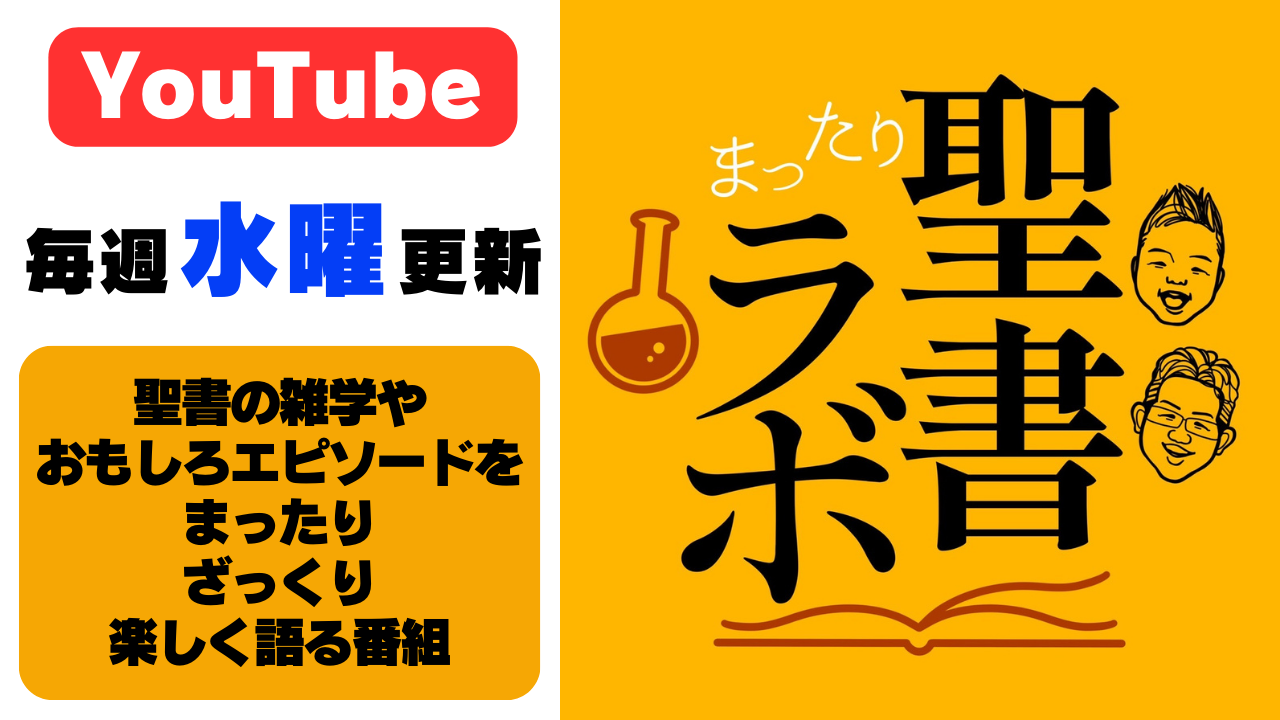励ましは人を立ち上がらせる

目立たなくても、誰かの人生を動かす「励ましの人」がいます。新約聖書に出てくるバルナバも、そんな人でした。彼の名前の意味は「慰めの子」。それは単なるあだ名ではなく、彼の人格そのものを表していると言えるでしょう。
バルナバはキプロス出身のレビ人ヨセフで、初めて登場する場面では、自分の畑を売り、その代金を献げるという寛大な行動をしています。信仰と愛に満ちた人だったことが、この行動から伝わってきます。彼は人々に頼られ、信頼されていた人物でした。
そのバルナバが大きな役割を果たしたのは、サウロ(後のパウロ)が回心して間もない頃のことです。かつてキリスト者を迫害していたパウロが信仰に立ち返ったとき、多くの人はそれを信じようとはしませんでした。しかし、バルナバだけは違いました。彼はパウロの変化を信じ、その証人となって弟子たちに紹介しました。その一歩が、後に世界を駆け巡るパウロの宣教の始まりとなったのです。
バルナバは、誰もが見逃してしまうような「人の中にある可能性」を見抜くまなざしを持っていました。そしてその可能性を信じて、支え、育てようとする人でした。アンティオキアで異邦人の信仰が広まり始めたときも、彼は派遣されて現地の人々を励まし、信仰にしっかりととどまるようにと勧めました。一人では足りないと感じると、わざわざタルソスにいたパウロを探し出して連れて来ます。ふたりで力を合わせ、そこで人々を教え、「キリスト者(クリスチャン)」という呼び名が初めて生まれるほどの共同体が形づくられていきました。
バルナバは、表舞台で注目されるようなタイプではありません。しかし、彼のような人の働きがなければ、信仰のバトンは繋がっていきませんでした。それは、子育てをしている母の姿とも重なります。母親の愛や励ましは、いつも表に出るものではないけれど、子どもの人生を根底から支えています。静かに、しかし確かな愛を持って、人を信じ、育てるという働き。その姿は、まさにバルナバそのものです。
後に、マルコという若者が宣教の途中で脱落し、パウロからは見放されそうになります。しかし、バルナバはマルコを見捨てません。再び彼を連れて旅立つことを選びます。時間はかかっても、人は変わる。そう信じたのです。結果的にマルコは成長し、晩年のパウロから「私の働きに役立つ人」とまで認められるようになります。さらに、マルコは『マルコによる福音書』の著者と伝えられるまでになったのです。
信仰を持って生きるということは、必ずしも人前で語ることではありません。職場で、家庭で、学校で、あるいは誰かのそばで、それぞれの生活の場で、信じて待ち、励ますこともまた、イエス様に従う生き方です。
イエス様もまた、人の中にある可能性を見つけ、愛によってそれを引き出された方でした。バルナバは、そんなイエス様の心をよく映し出している人だったのかもしれません。自分が目立たなくてもいい。誰かの背中をそっと押していく。そんな「励ましの人」がいることで、多くの人が立ち上がっていくのです。